採用のミスマッチはなぜ起きる?ブランド店から学ぶ“選ばれる採用”の考え方
DATE . 2025.10.19
Category : 採用戦略・採用ブランディング

Creative Director
株式会社アプリコットデザイン 代表
ブランドマネージャー1級/インターナルブランディング認定コンサルタント/WEBデザイン技能士/WEBマーケティング検定/ネットショップ実務士
DATE . 2025.10.19
Category : 採用戦略・採用ブランディング

Creative Director
株式会社アプリコットデザイン 代表
ブランドマネージャー1級/インターナルブランディング認定コンサルタント/WEBデザイン技能士/WEBマーケティング検定/ネットショップ実務士
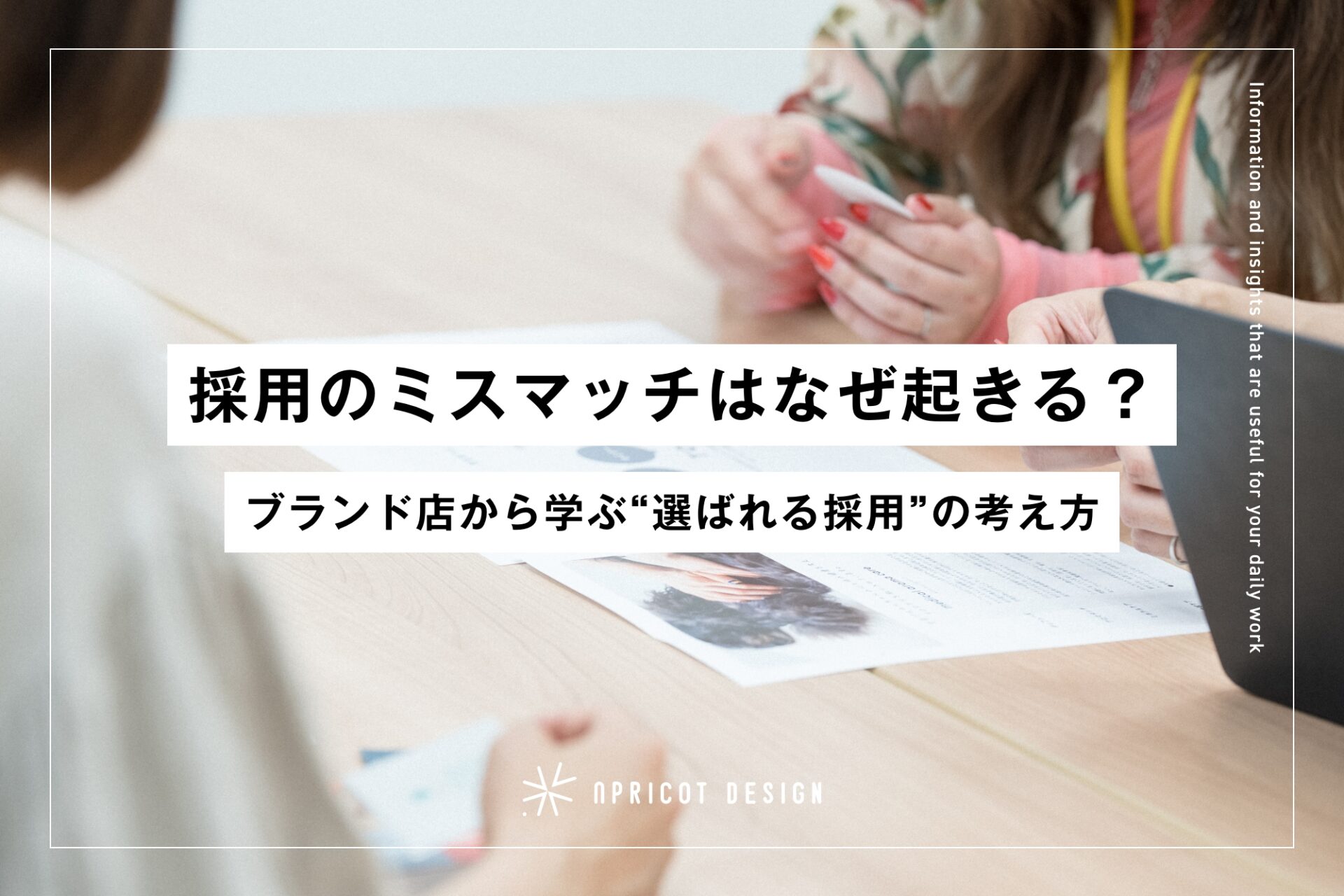
どうも、中村です!
今日は「なぜ採用でミスマッチが起きるのか?」についてお話しします。これは僕自身、経営者として採用に関わってきた中で実感したことでもあり、デザインやブランディングの仕事と共通しているテーマです。
Contents
採用の現場でよく耳にするのが、「せっかく採用したのに、すぐ辞めてしまった」という話です。企業側は「せっかく時間もお金もかけて採用したのに…」と落胆し、応募者側も「思っていた仕事と違った」と感じてしまう。いわゆる“ミスマッチ”です。
では、なぜこのようなことが起きるのでしょうか?
僕が思う大きな原因の一つは、募集の段階で「誰でもいいから応募してね」というメッセージを出してしまっていること。要するに「うちで働けばこんなにいいことがありますよ」とメリットばかりを並べて、本当に必要な人材像を描けていないんです。
ここで一つ、身近な例を出してみます
ブランド品のお店って、誰にでも「買ってください!」というスタンスではありません。むしろ「私たちの商品を理解して、大切に扱ってくれる人に届けたい」という考えが前提にあります。だからこそ、店構えや接客、雰囲気にいたるまで「私たちはこういうお客様をお迎えしたいです」というメッセージが明確なんです。
一方で、万人向けのブランドはどうでしょう?より幅広い層にアプローチする分、多様なお客様が集まります。もちろんその分売れる数も多くなりますが、同時に「自分には合わなかった」と感じる人も増える。これは採用にもそのまま当てはまるんです。
企業が採用活動をするとき、「自社の魅力を伝えること」に力を入れるのは当然のことです。ですが、実はそれだけでは不十分です。なぜなら“いいところ”だけを伝えると、応募者は理想像を膨らませすぎてしまうからです。
たとえば、ある会社が「フラットで自由な職場です!」とだけ伝えたとします。でも、実際に入ってみると「自由というより放任で、自分から動かないと誰も助けてくれない」なんてこともある。これって、ある人にとっては魅力(=自立できる環境)ですが、別の人にとっては苦痛(=サポートがない環境)なんですよね。
つまり、会社の“悪いところ”を隠すのではなく、むしろ「うちではこういう部分が大変かもしれません」と正直に伝えることが、ミスマッチを減らす最大のポイントです。
僕が経営の中で学んだのは、「悪い」と思える特徴も、人によっては「むしろそこがいい」と感じる場合があるということです。
例えば、
このように、同じ事実でも受け取り方は人によって真逆になります。だからこそ、採用時には「うちの会社にはこういう特徴があるよ」とニュートラルに伝え、その特徴を望む人に来てもらうことが大事なんです。
僕はデザインやブランド戦略の仕事を通して、「誰に届けたいのかを明確にすること」がすべての基本だと考えています。採用も同じで、「どんな人に来てほしいのか」を言語化し、発信することが欠かせません。
そして、これは単なる求人広告の書き方ではなく、会社の姿勢そのものに表れるんです。ブランド店が「お客様を選ぶ」ように、採用も「私たちはこういう人と一緒に働きたい」と打ち出す。そうすれば自然とミスマッチは減り、長期的に会社も人も幸せになれるわけです。
では、具体的に今日から何をすればいいのか?
僕のおすすめは、まず 「うちの会社に合わない人」を書き出してみること です。
このように「合わない人」を言葉にすることで、逆に「合う人」が明確になってきます。その上で、求人ページや説明会、面接などで正直に伝えてみてください。それだけでも、採用後のギャップをかなり減らせます。
どうでしょうか?採用のミスマッチは、避けようと思えばある程度は避けられるものです。ポイントは「いいところ」だけではなく「特徴」をありのままに伝えること。そして「来てほしい人」を明確に描くこと。
ブランド店がそうであるように、企業も「誰でもいいから」ではなく「私たちはこういう人を待っています」と発信していきましょう。
それでは、また!