見やすいデザインの秘密とは?情報整理がもたらす驚きの効果
DATE . 2025.10.09
Category : ブランディングデザイン

Creative Director
株式会社アプリコットデザイン 代表
ブランドマネージャー1級/インターナルブランディング認定コンサルタント/WEBデザイン技能士/WEBマーケティング検定/ネットショップ実務士
DATE . 2025.10.09
Category : ブランディングデザイン

Creative Director
株式会社アプリコットデザイン 代表
ブランドマネージャー1級/インターナルブランディング認定コンサルタント/WEBデザイン技能士/WEBマーケティング検定/ネットショップ実務士
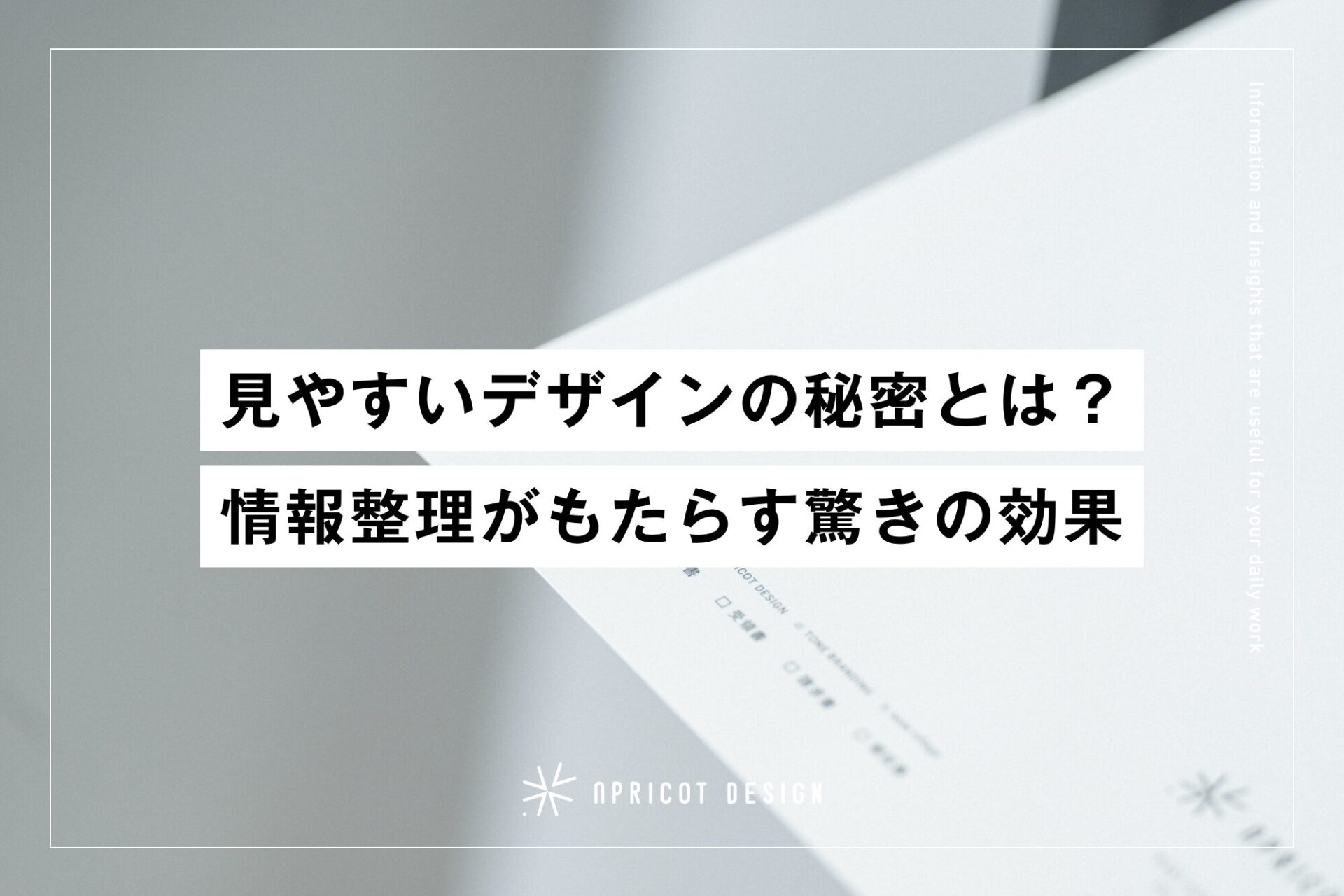
どうも、中村です!
デザインの仕事をしていると、「見やすいですね!」「わかりやすい!」というお声をいただくことがあります。特に、アプリコットデザインの制作実績に対して、そのような嬉しい感想をよくいただきます。でも実は、それって“センス”だけの問題ではありません。
今回は、「見やすいデザイン」と「見ずらいデザイン」の違いについて、脳の仕組みや情報整理の観点から解説してみたいと思います。
まず最初に理解してほしいのは、デザインにおけるすべての要素、線も、色も、イラストも、写真も、文字もすべてが「情報」だということです。
たとえば、ページの中に1本の線が引かれているとします。その線には、「ここで区切られている」「ここは違う情報だよ」といった意味が含まれます。つまり、線1本でさえ、見る人の脳に何かしらの“メッセージ”を届けています。

逆に言えば、線が多すぎたり、写真が多すぎたり、色がバラバラだったりすると、それだけで脳は混乱してしまいます。情報が多すぎると、「どこを見ればいいのかわからない」「何が重要なのかわからない」となってしまい、結果的に“見ずらい”と感じるのです。
人間の脳は、なるべくエネルギーを使わずに情報を処理しようとします。わかりやすく言うと、「めんどくさがり」なんです(笑)。
たとえば、雑多なスーパーのチラシを見ると、商品はたくさん載っているけど、結局どこに何があるのか一瞬ではわかりませんよね?これは、情報が多すぎて脳が処理しきれないからです。
反対に、白をベースに余白を活かしたスッキリとしたデザインは、視線が自然と目的の場所に導かれるので「見やすい」「わかりやすい」と感じられます。
多くの人が「良かれと思って」情報を足してしまいがちです。
たとえば
でも実際は、情報を足すほどに脳への負担が増え、伝えたいことが埋もれてしまいます。
だからこそ、僕たちは常に「引き算」を意識しています。本当に伝えたいことは何か?そのために必要な情報だけを厳選し、それ以外は思い切って削る。それが、結果的に「見やすいデザイン」につながるんです。
たとえば、以下のような2つのチラシを比べてみてください。


同じ内容を伝えていたとしても、Bの方が圧倒的に「伝わる」し、疲れないんです。
僕が大事にしているのは、「デザインとは目立たせること」ではなく、「伝えるべきことを、正しく、素早く、ストレスなく届けること」だという考え方です。
見やすいデザインの根本には、“情報の整理整頓”と“無駄を削ぎ落とす引き算”がある。
それを意識するだけでも、今よりずっと「見やすいデザイン」を作れるようになりますよ。
それでは、また!